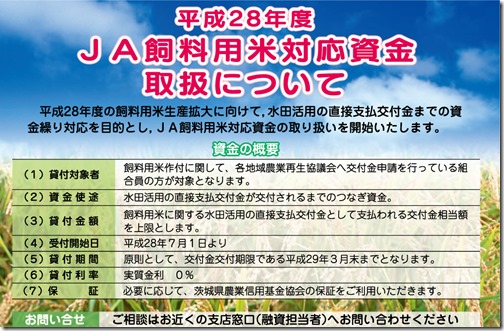- 平成29年産米の生産対策について
- JAグループ茨城 「JA自己改革実践大会」を開催
- ニュース&トピックス
- くらし女性部
- みんなのひろば
- 専門業務従事者のご紹介
- 新鮮食材で楽しくクッキング
- 季節を詠む
- おたより
- インフォメーションボックス
- 旅のご案内
- 住宅リフォーム案内
カテゴリー: トピックス
「茨城をたべよう収穫祭」は茨城県のおいしい農畜産物や加工品をPRして、地産地消を応援するイベントなんだ!いっぱい人がいたな~迷子になりそうだったよ


県西うまいもんストリートでは北つくば、常総ひかり、茨城むつみ、岩井の県西地区JAの皆さんがタッグを組んで、オリジナルブランド「ラ☆ウエスト」の農産物をPRしてたよ!
メロンや梨が当たるスピードくじは大人気だったよ~


茨城県のJAや生協、漁協、森林組合などで作る「協同組合ネットいばらき」のコーナーも賑わっていたよ。JA北つくばのブースではイベントで新米のすくい取りをしていたよ。JA北つくばの美味しいお米をたくさんの人に味わってもらいたいから、僕も応援したよ~。
みんな上手にすくっていたから、予定していたお米がどんどんなくなって担当者の顔が青くなってた!




おとなりのJA常陸さん。特産品の「笠間の栗」を焼き栗で販売してたよ。とっても甘くて、ホクホクして美味しかったな~。

JA茨城県厚生連のブースでは、血圧測定や健康相談をする人でいっぱい!
 JA茨城県中央会のみなさんもいたよ。茨城の農産物で作ったお酒をPRしてたよ!
JA茨城県中央会のみなさんもいたよ。茨城の農産物で作ったお酒をPRしてたよ!
 生協のみなさんもがんばっていました。美味しいカレーをいただいたよ。
生協のみなさんもがんばっていました。美味しいカレーをいただいたよ。
 下妻市のイメージキャラクター「シモンちゃん」も遊びに来ていたよ~
下妻市のイメージキャラクター「シモンちゃん」も遊びに来ていたよ~

JA岩井さんの「ネッキーマン」も大人気!かっこよかったな~
 県西4JAの職員で作る「ラ☆ウエストガールズ」の皆さんも県西地区の農産物をPR!がんばっていましたよ~
県西4JAの職員で作る「ラ☆ウエストガールズ」の皆さんも県西地区の農産物をPR!がんばっていましたよ~

- JAバンク ウィンターキャンペーン
- 改正犯罪収益移転防止法のご案内
- ニュース&トピックス
- くらし女性部
- 新鮮食材で楽しくクッキング
- みんなのひろば
- 東部トマト選果場視察研修を受入れ
- 専門業務従事者のご紹介
- 季節を詠む
- おたより
- インフォメーションボックス
- 旅のご案内
- 農業まつり日程
| 【平成28年度 農業まつり開催日時・場所一覧】 | ||||
| 開催地区 | 開催日 | 曜日 | 開催時間 | 開催場所 |
| 結城 | 11月3日 | (木) | am 9:00 ~ pm 3:30 |
結城支店敷地 |
| 関城 | 11月12日 | (土) | am 9:00 ~ pm 3:00 |
関城共同梨選果場 |
| 協和 | 11月19日 | (土) | am 9:00 ~ pm 3:00 |
協和野菜出荷場 |
| 下館 | 11月19日 | (土) | am 9:00 ~ pm 4:00 |
筑西市運動公園東側 |
| 11月20日 | (日) | am 9:00 ~ pm 3:00 |
||
| 明野 | 11月23日 | (水) | am 9:00 ~ pm 4:00 |
明野支店敷地 |
| 岩瀬 | 11月26日 | (土) | am 9:00 ~ pm 3:00 |
岩瀬西部ライスセンター敷地 |
| 大和・真壁 | 11月26日 | (土) | am 9:00 ~ pm 3:00 |
大和きゅうり選果場 |
すてっぷ10月号の18ページ「きらいちイベント案内」の記載に誤りがございました。
皆様にご迷惑をおかけしたことを、深くお詫び申し上げます。
「きらいち」筑西店5周年感謝祭開催日
◆ (誤) 9月29日~30日 → (正) 10月29日~30日
JAファーマーズマーケット「きらいち」はオリジナルブランド商品「きらいち中濃ソース」を、栃木県佐野市でミツハソースなどを製造販売する早川食品(株)と共同で開発、商品化しました。
ソース開発は、6次産業化と地産地消活動への取り組み。JA北つくば管内で収穫された玉ネギ、ニンジン、トマトなどが原料です。ソースの種類は関東地方の主流である中濃ですが、一般的な中濃ソースよりもとろみを抑え、中濃とウスターの中間に濃度を調整しました。また、製造する早川食品が使用する水は、日本名水100選に選ばれる佐野市の「出流原弁天池湧水」。この良質な水が、野菜の旨味を引き出し、甘さの後に少し辛さが残るスパイスを利かせた味に仕上げています。
ソースは料理の必需品!きらいち筑西店・結城店で1本税込450円(300ml)販売していますので、是非、ご賞味ください。

僕はとんかつが大好き!きらいちソースでおいしいくいただくよ~

- JAローンのご案内
- ニュース&トピックス
- 特集1:おにぎりダイエット
- くらし女性部
- 専門業務従事者のご紹介
- みんなのひろば
- 特集2:ふれあいイベントを開催
- 新鮮食材でたのしくクッキング
- 季節を詠む
- おたより
- インフォメーションボックス
- 旅のご案内
- ホームヘルプセンターからのお知らせ
JA北つくばのホームページをご覧いただき誠にありがとうございます。
この度、平成28年9月1日よりJA北つくばの公式ホームページをリニューアルいたしました。
今回のリニューアルでは、より快適にお使いいただくため、デザイン、構成を見直しスマートフォンによる閲覧にも対応いたしました。
今後とも何卒宜しくお願い申し上げます。
こんにちは。
ぼくがついに3Dになったよ!

これからは色々な所に出かけて、JA北つくばの楽しい情報をお届けできればと思います。
たくさんの人に出会えるといいなぁ~。

JAと北つくば農協葬祭(株)は6月14日、桜川市中泉で葬祭場「JAホール岩瀬」の新築工事の起工式を執り行いました。関係者ら約50人が参列し工事の安全を祈願しました。
JAホール岩瀬は同市御領で、民間の葬祭会社とホールを共同で使用し、事業を展開していましたが、更なる利用者へのサービス向上を目的に移転します。新ホール建設地は国道50号線、北関東道・桜川筑西インターチェンジのほど近く。同JA管内の大和地区、協和地区にも隣接しており利用しやすい立地条件となっています。新ホールは鉄骨造平屋建て、延べ床面積が約1698平方メートル。完成は来年1月末を予定します。
起工式に参列した國府田利夫組合長は「組合員や地域住民から利用しやすく、選ばれるホールを目指して運営協力をしていきたい」とあいさつしました。